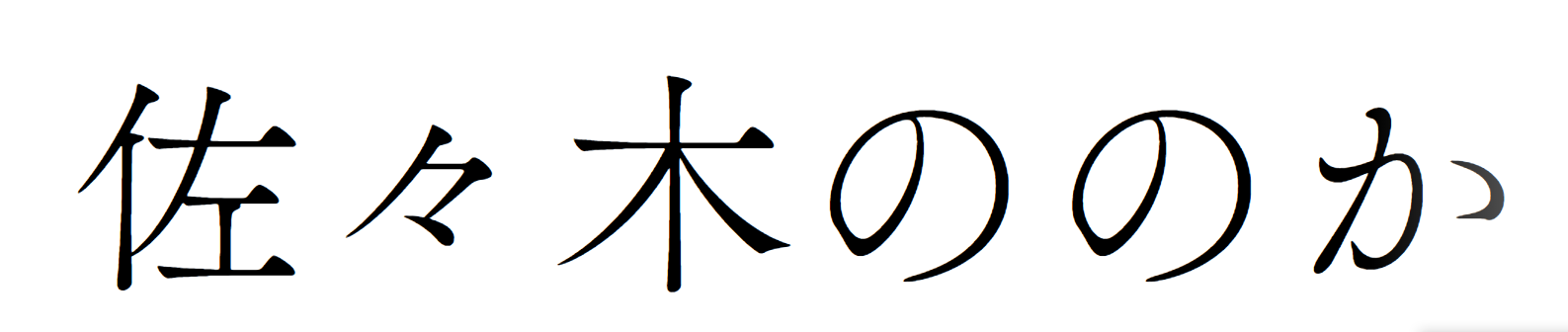辺鄙な山奥で、猫二匹、馬一頭とともに暮らしている。こう言うと、穏やかでいい暮らしですねとでも言われそうだし、実際に野山の生活は退屈地獄とも言うべき凪の楽園だが、私が気に入っているのはそうした穏やかさだけではない。むしろ、己の野蛮さを発揮できるところに、この生活の醍醐味があると感じている。
たとえば、おてんば盛りの猫たちは、よく食べ物を盗み食いする。あるときは翌日のためにと作っておいたスープが入った鍋の蓋を開け、ご丁寧に素手でかき回してくれた。またあるときは庭で獲れたとうもろこしを茹で、ザルに入れたまま冷ましていたところをやられた。ちなみにとうもろこしが相当気に入ったようで、ちょっと齧っただけで済ませず、ころころと回して一周食べ尽くしていた。このときばかりは器用に食べるねと感心してしまったけれど、それ以外にも勝手に炊飯器のスイッチを押してご飯を炊いたこともあったし、脱衣場で脱いで置いておいたストッキングをくわえて二匹で綱引きしていたこともある。
こうした猫たちの悪行はおおむね許せるのだけれど、先日どうしても許せなかったのは、私が隣町まで三十分かけて買いに行ったパイナップルケーキを猫が見つけ出し、夜中にこっそり食べていたことだった。百六十キロ先の札幌のお店がたまたま委託販売していた限定商品で、発売日の前からずっと楽しみにしていたものだ。私は「ああ」という大声に落胆と憤りを滲ませて、ケーキを食べたであろう猫に「しばくぞ」と怒鳴った。猫はちょっとだけ申し訳なさそうな顔をして、首を引っ込めた。私は彼女たちの保護者で、人間なのだし、言葉で言ってもわからぬ動物相手に怒っても仕方ないであろうと思われるかもしれないが、私はこのように喧嘩する。
馬のペリートが牧草をよこせと私の恥骨を目掛けて頭突きしてきたときも、あまりの痛さに「てめえ」と叫んでしまった。しかし、ペリートも負けじと私が抱えた牧草を奪いにくる。猫ならばひょいと抱え上げて「ダメだよ」と言えば済むのだが、馬となればそうはいかない。それに、馬は猫以上に、あるいは人以上に、人間の気持ちが伝わってしまう。心の内まで気を抜かず、真剣に対峙しなければ、見透かされて見放される。その嘘のなさが、私にはたまらなく心地いい。
私は人とうまくやるのが苦手だ。厳密に言うと、表面を繕って人とうまくやることはできるのだけれど、ある一定以上の近さに入られると、途端にうまくやれなくなってしまう。良い人を装うことで綻びが徐々に大きくなり、爆発する。 私が全力で憤ると、ほとんどの相手は立ち直れなくなり、人間関係が終わる。「あんなにやさしかったのにどうして」「騙された」と言う人もいる。そのたびに、私はかなしくなる。何一つ伝わっていなかったのだと。
あるいは、相手が私に対して何か思うことがあるとして「こんなことを言ったら可哀そうだから」という遠慮をされるときにも腹立たしさを感じる。手加減をするということは、相手をナメてかかっているということだ。それに「可哀そう」と思うときは大抵、相手を慮っているようで、その人自身が悪者になりたくないがゆえの自己保身でそうしている。それなのに、「可哀そうだから」などと善人の雁首さげて、こちらが怒る機会も、傷つく機会も奪うなんて卑怯極まりない。私なら、大事な人ほど真っ向からボコボコにする。必要ならば、相手の拳を受け止める。それが対等な存在に対する礼儀であり、やさしさだ。人間相手だと、それが「暴力」として受け取られてしまうが、動物たちとのかかわりの中では、それができる。
動物たちと言葉を交わすことはできない。しかし、本気のコミュニケーションをとること、すなわち喧嘩することはできる。お互いの欲望をぶつけ合い、火花を散らし、何事もなかったかのように頬ずりをし合う。彼女たちと一緒に過ごしていると、たまらなく生きている実感が湧く。そうして、ずっと、寂しかったことを知る。